山形で春を告げる野菜と言えば一番最初に思い浮かぶのがあさつき(浅葱)、昨日食卓に登場しました、山形が主産地で5割を占めるそうです
青い部分をみじん切りにして薬味として使うイメージが強いですが、このへんの地方では太い根に近い白い茎部分を食すのが特徴です。あさつき(浅葱)はもともとは、山の草地に生えている野草のひとつだそうですが、最近は栽培も盛んでスーパーなどでも手に入れることができるようになりました。 食べ方は薬味として使うほか、サラダやあえものに加えたり、焼き肉や刺身で巻いていただくのもおすすめのようです。ワタクシ的には歯ざわりと香りの高さが生かしたた食べ方として酢味噌和えが一番のお気に入りですが、お吸い物もいいですね。 あさつき(浅葱)は効用として「気を下し、食を消し、また能く食を進める」とあり、あさつき(浅葱)は古くから食欲の増進に役立つことで知られ、他に利尿・発汗に作用したり、ストレスを防いだりします。疲労回復などにも効果があるそうです、おしまい。 |
また山の達人から、あけびを沢山いただきましたので、山形の代表的郷土料理「あけびの肉詰め」に挑戦です。と言ってもワタクシが作ったわけでありませんが…w。
アケビの皮に、ひき肉やピーマン等を甘味噌であえて詰めたものを油で炒めるだけ、「ほろ苦さ」と「ソフトな食感」が季節を感じさせてくれます。ポイントは、水気をとったアケビの皮の内側に小麦粉を振り、肉餡を詰める。具が飛び出さないよう真ん中でタコ糸で縛り、油で揚げてOK。 山形では、中の白いところは食べないで捨てますが、よその土地では中の白いところを食べて、皮を捨てる「所変われば品変わる」ですね。 |
春の息ぶきとともに、昼休みのウォーキングを再開しましたが、水墨画の世界から飛び出したようで実に気持ちよい。今日、いつものウォーキングコースを変更してみたら、あおさぎの巣窟と遭遇。
これまでも時たま、川辺で小魚捕りをしている姿を見かけてたので、この辺りに自宅マンション?があるとの想像はついてましたが、ついに発見!夏は葉っぱに覆われて気づきませんでしたが、なんと過密住宅のような満室状態ではないか。これから繁殖時期に入るそうで、せっせと巣作りをしていました。偽装耐震で揺れ動く人間社会をよそ目に、鳥類の世界ではこの程度の過密は大丈夫なのかも…あおさぎはコロニー(集団繁殖地)をつくることが多いと聞いていましたが、正にそのとおりでした。 あおさぎは日本で最も大きいサギといわれ、体は灰色で、飛ぶと黒が目立つ。よくみると頭に黒い冠羽があり、眼の上にも黒い模様がある。一見、ツルのように見えるが、れっきとしたサギ。木に止まることができるのと、飛ぶ時に首をS字型に曲げる点がツルでない証拠。白鳥が北へ帰ってしまった今、今度はあおさぎがウォーカーの目を楽しませてくれるに違いない。 |
この人だれやねん、MRマリック?ブブッー。
若い方は知ってるでしょうか、因幡晃ですよ。 昨夜、NHKTVで東北出身のちょい昔の歌い手がワンサカ出てましたね。因幡晃のほかに藤あや子、佐藤宗幸、新沼謙治…おらが大泉逸郎出てなかったのが残念! ところで歌って、メロディと詩がマッチしてこそナンボじゃありません?いろいろ時代とともに流れてきましたが、おやじ的にはフイットするのが因幡晃の「わかってください」ですね。 お隣秋田県の出身で、なおかつ鉱山労働者出身という親近感、それに「♪涙で文字がにじんでいたなら…」なんてくさい詩は、今時ありえないでしょうよ。ですから何年に1回か、くさい歌を無性にうたいたくなるんです。それでは、ご一緒にご唱和お願いします。 ♪貴方の愛した 人の名前は あの夏の日と共に 忘れたでしょう いつも言われた 二人の影には 愛がみえると 〜中略〜、↓からサビ これから淋しい秋です ときおり手紙を書きます 涙で文字がにじんでいたなら わかって下さい 誰か止めてくれ〜〜〜 |
|
日本中がアツク燃えたWBC、王ジャパンは首の皮1枚残して韓国から劇的勝利、そして今日の決勝戦、キューバ相手に見事世界一…パチパチパチ。アメリカの審判の誤審問題もあって、後味の悪さを引きずった大会でもありましたが、それを吹き飛ばして余りある優勝でした。
その誤審問題ですが、アメリカ戦での3−3と同点の場面、3塁ランナーの西岡がタッチアップしし、ホームを駆け抜けたその時、誰もが日本の勝ち越しを確信したことでしょう。しかし、米国チームはタッチアップが早いと抗議しました。何と、この抗議で、一度はセーフとされた判定が、その後、アウトと覆ってしまったのです。 私は、長い間野球を見続けてきましたが、監督の抗議で判定が覆ったのを見たことはありません。「審判は絶対ですから、覆りませんよ」というのが、解説者の説明です。相撲のように、ビデオを見て審判団が協議すればいいのにと、私などは思いますが、そうはいきません。 一度、下された審判の判定が覆るというあり得ないはずの事態が生じ、しかもそれが野球の本場、アメリカでのことなのですからなおさらです。 もし、日本チームからの抗議だったら、このような形で判定は覆ったでしょうか。それが米国チームからの抗議だったからだと、どうしても思いたくなってしまいます。 公正で公平な審判というのは、スポーツの大原則です。どこの国のチームであれ、そのような原則を適用するのが、フェア・プレーの精神でしょう。 アメリカは、いつの間にか、このような精神を失ってしまったのでしょうか。自国のチームや選手をえこひいきする国に成り下がってしまったのでしょうか。世界の大国という「ハードパワー」に頼り続けてきたために、アメリカの人々は「ソフトパワー」の威力を忘れてしまったのかもしれません。しかし、アメリカは格下メキシコに思わぬ敗退を喫し、「想定外」脱落は皮肉というしかありません。でも、「雨降って地固まる」でニッポンが勝ったから、まっいいか〜。 |
昭和な話1回目。今から40年以上も前にアイビールックが流行したのを覚えているだろうか?当時高校生だった自分は「VAN」に、心の底から憧れたものである。おしゃれにめざめた頃でもあり、VANの洋服が欲しくてしかたがなかったが、でも値段が高くてとても手が出なかった。だから、比較的お坊ちゃんのおしゃれ振りを指をくわえて見てるしかなく、ファッション誌「メンクラ」をながめては我慢したものだった。
とにかくVANは高かった。なけなしの小遣いを貯め込んではVANのシャツを買い、それを学校で見せびらかしたものだ。また「VAN」の紙袋(紙袋の中身は弁当しか入ってなく、時々汁が漏れちゃたりして…w)を抱えて通学したのを覚えている。ただジャケットだけは高くてどうしても手が届かなかったな〜。 アイビー・ルックの影響だろうか、今でもブレザーやボタンダウン・シャツ、レジメンタル・タイは好んで着るから「三つ子の魂百まで」といったところか。ただ、おじさんになって腹もせり出してくると、ジャンパーやチノパンでおしゃれしたつもりでも、「それ作業着?」と聞かれてガッカリすることも…。 当時の服は残ってる由もないが、リーガルのローファーはまだ残っています(奇跡ぃ)。それがこの写真のもので、保存状態もいいでしょう、ワタクシのお宝です。おじさんにも、そんな時代があったのです、信じられないでしょうけど…。 |
焼きそばUFOを前にして、ふと思い出しました。実は何を隠そうワタクシUFOを見たことがあるのです。マジです、トルーですよ。
場所は自宅寝室から見えたので、すぐそば…寒河江市大字高屋付近ですよ。 あれは忘れもしない平成元年ころかな、真夏の明け方でした。まだ薄暗い3時ころでしょうか?熱帯夜のためまんじりともせずに、ふとねぼけ眼で窓の外に目をやると星の一つが左右上下に激しく動いてるではないか?これは夢かまぼろしか?目をこすって何回も凝視しましたが、5分間くらい呆気にとられて見ていました。 ふと我に帰り「これはてえへんだ、UFOだ〜」とカミサンを無理やり起こして再び外に目をやると、UFOらしき物体はあとかたもなく消えていました、超常的な現象との遭遇葉はこれが最初で最後でしたが、その後TVのUFO特集番組で似たような目撃証言がレポートされておれましたので、あらためてあれは間違いなくUFOだったんだ、と確認したところです。 おそらく誰も信じてくれないと思いますが、カミサンは見てはおりませんが、義理?で信じてくれてるようです。この体験をしてから、いわゆる世の中にはありえないようなことが現実にあるんだということを思うようになりました、おしまい。 |
今日は久しぶりに予定なしで、雨降りも重なってゴロ寝サンデー。
こうなるとTV見てるしかありません。アンビリーバボーの再放送で、館林さんという女子高校生が自動車事故で受けた頚椎損傷という障害による絶望の日々から家族や友人との葛藤、そして介助犬アトムとの運命的な出会い、そしてアトムと共に学び歩んだ大学生活…そんなドキュメントでした。 彼女と介助犬の関係は、「一方的に介助犬から何かしてもらうではなく、何をしてあげられるか」とインタビューで答えていたように、当事者でしか理解できない対人間以上の絆の強さを感じました。 もし、自分が交通事故に遭って車椅子生活しかできなくなったら…「彼女と同じように立ち直ることができるだろうか?」「いくら家族の手助けがあっても、身の回りのことなどで負担をかけてしまう」という現実に耐えることができるのだろうか…と逡巡しました。 でも、あのハンディを感じさせない頑張る姿は、ブラウン管を通してですが、生きるために必要な勇気メッセージそのものでした。日常の雑事に流されて、大きなことが見えなくなり小さなことに悩んでる自分…滑稽に見えて、足もとを見つめ直す意味でいい番組でした。 |
|
「三つ子の魂百までも」などと申しますが、この年になっても小さい頃に憧れた、まぼろし探偵や月光仮面などの漫画のヒーロー達には胸トキメクものがあったりします。手に汗握る敵との死闘などなど、現実を忘れ子供の頃に“ごっこ遊び”で真似していた、あの世界…。嗚呼…(遠い目で)
なぜ、突然こんな話を始めたのかといいますと、仲間由紀恵、オダギリジョー出演。後のヒーローもの少年漫画などに多大な影響を与えた忍者活劇小説シリーズ、山田風太郎さんの「甲賀忍法帖」を原作にした映画「SHINOBI」を見てきました。 そこに映し出されていたのは、紛れもなく“ごっこ遊び”の時、脳内に思い描いていたヒーロー達の戦いでした。華麗なコンピュータグラフィックスで描かれる伊賀vs甲賀の忍者バトル。「うわ、有り得ねぇ」というようなカッコイイ必殺技の数々…。さしずめ、白土三平さんの漫画「カムイ伝」の実 写版とでも例えましょうか。ん?例えが悪いですか? とにもかくにも、あ、そういえばオダギリジョーさんは「仮面ライダークウガ」というヒーローでデビューしたんだっけ。ううむ、やはりオダギリはヒーローが似合うなぁ。などと思いながらドキドキと手に汗握りつつ、映画「SHINOBI」を満喫してきたワタクシです。 こんな書き方をすると「単なるヒーローアクションもの?」と誤解されてまいそうですが、さにあらず。主題歌はなんとあの浜崎あゆみさん!まさに今が「旬」の出演者の方々の熱演!そしてラブストーリー!…と、幅広い年齢が色々な観点から楽しめる映画でしたよー。みなさんも忍(しのび)の世界に旅立たれてみてはいかがでしょうか? |
昨日はお盆礼で、カミサンの実家へ…そして年に1度あるかないかの、ズワイとのご対面、し、しかも一人に1ぱいづつ。
ワタクシは食べることに関してはすごく執着する食いしん坊なのですが、面倒な食べ物が苦手です。 食べる前に何か作業を必要とするもの(カニとか、骨がたくさんある魚)や、手が汚れる食べ物(スナック菓子)とか。 人は自分で殻からむいて食べるからこそ美味しいんだよ!と言いますが、あの黙々と作業する時間がもったいないというか、せっかちなんでしょうね。人によっては、味噌嫌いな人もいるし、足はいらんって言う人もいるし、そういう人たちは、二人で一匹でいいじゃん!そういうもんでもないか(笑)。 もちろん全然食べれない人もいるんだけどね、そういう方は是非ご一報ください。 |
ワタクシたち60年代の男の子の遊びの定番といえば、メンコに尽きるでしょう。今の子供たちはメンコを見たこともないでしょうが、当時男の子が2〜3人集まれば、必ず、このメンコで遊んだものであります。
オーソドックスなものが角型のやつで、他に大ワンという丸型のものもありました。モノによって硬さと大きさが違い、表面には、当時の人気キャラクターが描かれ、裏面にはナゾナゾが書かれていたり、ちょっとした豆知識のようなものが書かれ、さらには、ジャンケンのグー・チョキ・パーの手の形や、数字の羅列されたものが書かれていたものもありました。 メンコの一般的な遊び方としては、自分のメンコを相手のメンコにぶつけて、相手のメンコを台から落したり、裏返したりすることが出来たら、自分の勝ちで、そのまま、相手のメンコを貰えるというようなルールで遊んでいました。 「月光仮面」が放映されていた頃には、我が家には、まだテレビがなく、「月光仮面」は近所のTVあるお宅に図々しくも「スミマセーン、テレビ見して下さ〜い」と言いながら、ドヤドヤと上がり込み、胸をときめかせながら見ていたものであります。 こうした人気番組のキャラクターが写っているメンコは、単に、遊びの道具としてだけでなく、いわゆるブロマイド代わりにコレクター・アイテムとしても重要な役割を果たしていたものでありました。メンコには、色々な細工を施して戦いにも強いメンコに仕立て上げ、得意になっていたものです。 メンコを強化する手法としては、メンコに油をしみこませて重くすると同時に、裏に紙を貼り付けて補強するというような手法が一般的なものでありました。だが、戦いに負けて、その大切な大切なメンコを他人に取られてしまったときは、2〜3日ショックから立ち直れなかったものです。 ...もっと詳しく |
最近「1リットルの涙」というドラマを見ました。私は、ふだんTVドラマなどを見る機会が少ないのですが、とても感動させられました。普段何気無く生活していると、気づかない大切なコトをたくさん教えてもらったような気がします。
いつも一緒にいてくれる家族や友人の大切さや、普通に歩けて話せるということの大切さ。普通であるということは、空気のように当たり前に考えていたけれど、本当は当たり前ではなく、偶然が重なって今の普通があるのかもしれません。普通でいれることがどんなに幸せなことなのかを感じさせられる、素敵なドラマです。 原作は、難病と闘いながら、ひたむきに全力で生きた姿が感動を呼び、160万部のベストセラーとなった愛知県豊橋市の木藤亜也さんの著書「1リットルの涙ー難病と闘い続ける少女亜也の日記ー」ということもドラマを見てから知りました。木藤さんは、中学3年生で「脊髄小脳変性症」を発病し、手足の自由や言葉を奪われ寝たきりの生活となり、1988年、25歳でその生涯を閉じましたが、著書は14歳から21歳までの日記を中心に構成し様々な心情を克明に記されたものだそうです。40数年前に「愛と死を見つめて」という本もベストセラーになり、映画も大ヒット(吉永小百合主演)しましたが、あれも闘病に立ち向かう姿が感動的でした。今回も改めて生きる事とは何かを考えてみるには必見のドラマじゃないでしょうか。近じか映画化もされるようですが。 |
copyright/osamu


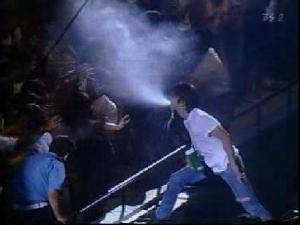





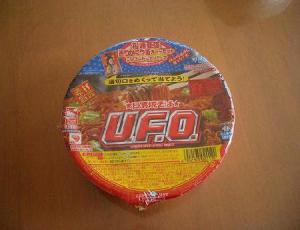


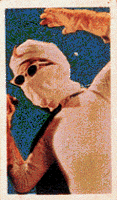





これはなつかし〜、生協お取りよせですが北海道産「北国のしばれあんだま」、ネーミングがスゴいですが甘いあんこを、しばれた(凍り付いた)という意味らしい。あんだまといえば鶴岡でも有名ななやつがあったような記憶が…。